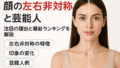「なぜ顎を引くと、二重顎が目立ってしまうのか…?」その疑問、実は多くの方が抱えています。顔写真を撮る時や、ふとした瞬間にスマホのカメラに映る自分のフェイスライン。実際【日本人女性の約4割が二重顎に悩んでいる】というデータも報告されています。
原因は、単純な「脂肪の増加」だけではありません。首や顎まわりの筋力低下、皮膚や脂肪のたるみ、ストレートネックをはじめとする姿勢不良、遺伝や加齢まで、複数の要素が複雑に絡み合っています。特に正しい姿勢を維持せずに長時間スマートフォンを使う現代人では、二重顎リスクが急増していることが、臨床医からも指摘されています。
「運動しても、ダイエットしても改善しない…」「写真に映る自分を見て落ち込んでしまう」そんな悩みをお持ちなら、専門的なメカニズムから見直すことが何より大切です。正しい知識と日常のセルフケア、そして必要に応じた医療的アプローチで、フェイスラインはしっかり変えていくことができます。
このページでは、通常は見過ごされがちな根本原因の科学的解説から、誰でも今日から実践できる予防・解消法、美しい写真のコツや最新治療法まで、徹底的にわかりやすくまとめました。
今の悩みの本当の理由や、その解決策を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
顎を引くと二重顎になる原因の科学的解説と身体メカニズム
顎を引く時に皮膚や脂肪が重なるメカニズム
顎を引くと二重顎になる現象は、首と顎をつなぐ皮膚や脂肪が一時的にたるみやすくなることが大きな要因です。顎下にはもともと脂肪が付きやすい部位があり、この脂肪が多いと顎を引いた時に重なりやすくなります。
また、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用による前傾姿勢は、皮膚や筋肉が緩みやすく、二重顎の形成を促す原因となっています。特にストレートネックの方は、顎を引いた時に首のシワやたるみが強調されやすい傾向にあります。
さらに年齢による皮膚の弾力低下も関与します。若い方でも、脂肪の蓄積や生活習慣次第で発生しやすくなるため、体型や年齢に関係なく注意が必要です。
筋肉の役割と顎下のリンパの流れの影響
あご下周辺には広頚筋(こうけいきん)やオトガイ筋(おとがいきん)など、重要な表情筋が配置されています。これらの筋肉が衰えることで、支えが弱くなり肌や脂肪がたるみやすくなります。
さらにリンパの流れが滞ると老廃物や余分な水分が溜まり、むくみとなって二重顎が強調されます。長時間同じ姿勢を続けたり、運動不足になることがむくみや筋力低下を招きやすく、日常の中で意識的に顎下の筋肉を動かすことが大切です。
下記の表で、主なリスク要因とその対策ポイントをまとめました。
| リスク要因 | 発生しやすい状況 | 対策ポイント |
|---|---|---|
| 筋肉の衰え | 運動不足、加齢、表情の乏しさ | 表情筋トレーニング |
| 脂肪の蓄積 | 食生活の乱れ、体重増加 | 食事管理・有酸素運動 |
| むくみ・リンパの滞り | 姿勢不良、長時間デスクワーク | 軽いマッサージやストレッチ |
| 皮膚のたるみ | 年齢によるコラーゲン減少、新陳代謝低下 | 保湿や顔のエクササイズ |
骨格の形状やサイズがもたらす影響
二重顎は脂肪やむくみだけでなく、顎の骨格や大きさにも強く影響を受けます。例えば顎が小さい、後退している、フェイスラインが丸みを帯びているといった骨格的な特徴を持つ方は、同じ体型でも二重顎になりやすくなります。
骨格は遺伝的要素の影響が大きいため、自分では改善しにくい場合もあります。ただし、表情筋の強化や姿勢の改善でフェイスラインをよりはっきりさせることは可能です。
骨格による二重顎が気になる場合には、セルフケアだけでなく美容クリニックでの相談も選択肢となります。脂肪吸引やリフトアップ施術、最新のハイフなど多様な治療法があるため、症状や悩みに合わせたアプローチが効果的です。
自分の顎や首の形に合わせたセルフケアと、必要に応じて専門家のサポートを活用することで、より理想的なフェイスラインを目指せます。
痩せているのに二重顎になる理由と特徴的なパターン
隠れ肥満や筋力不足以外の骨格的原因
痩せているのに二重顎が気になる場合、脂肪だけでなく骨格の特徴が大きな要因となっています。特に、顎が小さい、もしくは後退している場合は、皮膚や脂肪、筋肉の支えが少なくなり、あご下にたるみが生じやすくなります。歯並びや噛み合わせの悪さも、噛む筋肉や頬の筋肉をバランスよく使えず、二重顎が目立つ傾向があります。
下記のような特徴がある場合、骨格的な二重顎リスクが高まります。
| 骨格の特徴 | 二重顎リスク |
|---|---|
| 顎が小さい | 非常に高い |
| 顎が後ろに引けている | 高い |
| 噛み合わせが悪い | やや高い |
| 顎が細長い | 低い |
また、「痩せてるのに二重顎 直し方」や「顎が小さくて二重あご 解消」などの検索が多いのも、この骨格的要素が多くの方の悩みの根底にあるためです。
加齢による皮膚や筋肉の衰えと二重顎発生
年齢を重ねると、皮膚や筋肉に変化が起こりやすくなります。皮膚の弾力が失われ、フェイスラインが崩れやすくなったり、あごや首回りの筋肉が衰えてハリがなくなることで、たとえ体重が増加しなくても二重顎が目立つようになります。
特に40代以降は女性ホルモンの減少も影響し、脂肪のつき方や皮膚のたるみが加速します。下記に、加齢による変化のポイントを整理しました。
-
皮膚のたるみ:コラーゲン・エラスチン減少で弾力が低下
-
筋肉の衰え:表情筋・顎周辺の筋肉が動きにくくなる
-
脂肪の再分布:首元に余分な脂肪がたまりやすくなる
このような状態では、「顎を引く癖をつける」「顎を引く トレーニング」などのセルフケアが効果的です。習慣的に筋肉強化を行い、フェイスラインを引き締めていきましょう。
子どもや若年層でも二重顎になる要因
二重顎は中高年だけでなく、子どもや若い世代にも見られます。その主な理由は、遺伝や普段の姿勢、スマートフォン使用など現代特有の生活習慣に関連しています。特に「ストレートネック 二重あご 治った」「下を向くと二重あごになるのはなぜ?」などの問いが増えているのは、姿勢異常がもたらす現代的な問題を反映しています。
よくある原因
-
スマホやPC使用時の前傾姿勢
-
遺伝的に顎が小さい、骨格が小顔タイプ
-
あまり咀嚼しない食事習慣
-
運動不足や筋力低下
こうした場合、早めに正しい姿勢を意識し、「顎を引く 正しい やり方」やストレッチを習慣付けることが重要です。特に、子どものうちから顎や首の筋肉を動かすことを意識することで、将来的な二重顎リスクの予防にもつながります。
上記のように、痩せていても骨格・加齢・生活習慣が複雑に絡み合い、様々な年代で二重顎が発生しています。早めのセルフケアと正しい知識で、理想的なフェイスラインを目指しましょう。
ストレートネック・姿勢不良が及ぼす二重顎リスクの実態
ストレートネックによる筋肉のこわばりとリンパ滞留
ストレートネックは、現代社会で急増している姿勢異常のひとつで、首の自然なカーブが失われてまっすぐになることで、あご周囲の筋肉やリンパの流れに悪影響を及ぼします。首や肩の筋肉がこわばることで血流やリンパの循環が滞り、フェイスライン全体のむくみや脂肪の蓄積が進みやすくなります。その結果、痩せている方でも二重顎になりやすくなり、「顎を引くと二重顎になる」と感じる人が増加しています。特にスマホやパソコン作業で下を向く時間が長いと筋肉のバランスが崩れ、皮膚や脂肪が重力で下がりやすくなります。
下記のテーブルで、ストレートネックによる症状とそれが二重顎へ及ぼす影響をまとめます。
| 症状 | 影響 |
|---|---|
| 首・肩のこわばり | フェイスラインのむくみ、たるみの悪化 |
| リンパ・血流の滞留 | 脂肪・老廃物の蓄積、二重顎の目立ち |
| 姿勢のバランス崩れ | 顎下の皮膚・筋肉が下垂、表情筋の衰え |
正しい姿勢への修正法とセルフチェック方法
二重顎対策には、まず日常生活での姿勢の見直しが不可欠です。正しい姿勢は、頭・肩・腰が一直線に並び、耳の位置が肩の中央と垂直になる状態です。セルフチェックでは、壁に背中とかかとをつけて立ち、後頭部が自然に壁につくか確認しましょう。このとき、首だけが離れている場合、ストレートネックや猫背の傾向が強いと考えられます。
簡単なポイントをリストでご紹介します。
-
壁に後頭部・肩甲骨・おしり・かかとをつけて立つ
-
後頭部が壁につかない場合は要注意
-
モニターやスマホの高さを顔と同じ位置に調整
-
長時間同じ姿勢を避け、1時間ごとに軽いストレッチを行う
小さな意識の積み重ねが、二重顎のリスクを着実に減らします。
正しい顎の動かし方・癖づけ指導
顎を引く癖を意識することは、フェイスラインの美しさを保つためにも重要です。しかし、間違った顎の引き方で筋肉や関節に負担をかけてしまうと逆効果になる場合もあります。正しいやり方は、首の後ろが伸びて背筋がピンと伸びている状態で、軽く顎を後方に引き、首前面の筋肉で支える意識を持つことです。
注意点や効果的なトレーニング方法は下記の通りです。
-
強く引きすぎず、自然な範囲で行う
-
呼吸を止めないようにリラックス
-
毎日の洗顔後や鏡を見るタイミングで姿勢・顎をチェック
-
ストレートネック改善エクササイズや、フェイスラインのストレッチも取り入れる
日々の習慣に正しい顎の動きと姿勢意識を加えることで、二重顎の解消だけでなく、小顔効果や表情筋の若返りも目指せます。
写真や証明写真で二重顎が目立つ原因と対処法
顔の角度、照明、ポーズの影響分析
写真や証明写真で二重顎が目立つ主な原因は、顔の角度や照明、ポーズに深く関係しています。顔を下に向けたり、顎を強く引きすぎたりすると、皮膚や筋肉、脂肪が圧迫されやすくなり、二重顎が強調されることが多いです。また、横方向からの光や下からの照明はフェイスラインの影を作り、二重顎が目立ちやすくなります。下記の要因が特に影響します。
-
顎を引く姿勢になっている
-
ストレートネック傾向で首が前に出ている
-
下からの照明や強い横の光
-
無表情でいる、表情筋が緩む
短い撮影時間でもこれらの影響が大きいため、いつもの顔より二重顎が気になるという悩みにつながりやすいです。
美しい写りのための具体的なポージングテクニック
写真で小顔効果を高め、二重顎を目立ちにくくするには、正しいポージングが重要です。基本的なポイントを押さえておくと、どんな場面でも自信をもって写ることができます。
-
首をすっと伸ばし、背筋を伸ばす
-
やや顎を前に出し、顔を少し斜め上に向ける
-
口角を自然に上げることで表情筋にハリを持たせる
-
肩の力を抜き、リラックスする
下記のテクニックも効果的です。
- 指を鎖骨に軽く当てて顎をやや前に出す
- 自然な微笑みを意識
- ライトを正面から当てる
このような工夫で、フェイスラインが整い、二重顎がカバーしやすくなります。
証明写真やSNS用に使える補正グッズやアプリの紹介
近年は証明写真やSNS用の写真加工ツールも充実し、二重顎を簡単に補正できます。特に証明写真では顔の印象が大切なので、対策グッズやアプリを取り入れる価値があります。
| 補正アイテム | 特徴 | 利用シーン |
|---|---|---|
| 二重顎カバーテープ | フェイスラインを物理的にリフト | 証明写真や大事な写真撮影前 |
| 写真加工アプリ | フェイスライン・肌補整が可能 | SNS投稿、プロフィール写真 |
| スマホ用リングライト | 影を消し明るい印象をプラス | 自宅でのセルフ撮影全般 |
| 顎下リフトバンド | 顎下のたるみを一時的に引き締め | オンライン会議前、面接前 |
これらを活用すると、ストレートネックや姿勢が原因で二重顎になりやすい方でも、自然な印象に仕上がります。写真ごとに適切なアイテムや加工の使い分けがポイントです。
日常でできる二重顎予防・解消のセルフケアと生活改善策
塩分、水分コントロールとむくみ対策
日常生活で二重顎を防ぐためには、身体のむくみ対策が欠かせません。むくみの主な原因は、塩分の過剰摂取や水分不足です。塩分を摂りすぎると体内の水分バランスが崩れ、顎やフェイスラインに余分な水分が溜まりやすくなります。そこで、食事では減塩を心がけることがポイントです。外食や加工食品には多くの塩分が含まれるため、ラベルをよく確認し控えめにしましょう。また、必要な水分はこまめに補給することで、体内の老廃物や余分な塩分の排出を促進します。以下の生活習慣を意識することで、むくみのリスクが軽減できます。
| むくみ対策習慣 | 具体的ポイント |
|---|---|
| 塩分の摂取量を減らす | 加工食品・外食に注意する |
| こまめな水分補給 | 1日1.5~2リットルを目安に飲む |
| ビタミン・カリウム摂取 | 野菜や果物、海藻類を積極的に活用 |
| 適度な運動 | ウォーキングや軽いストレッチを取り入れる |
むくみが気になる場合は、寝る前に簡単なリンパマッサージもおすすめです。
顎まわりの筋肉を鍛えるトレーニング方法
二重顎は脂肪の蓄積や顔まわりの筋肉の衰えとも深く関係しています。適切なエクササイズで顎下や首回りの筋肉を強化すると、フェイスラインが引き締まりやすくなります。おすすめのトレーニングを紹介します。
- 舌回し体操
口を閉じたまま、舌を大きく10回右回り・左回りに動かします。 - あいうえお体操
表情筋を意識しながら大きく「あ・い・う・え・お」と5回ずつ発声します。 - 顎引きトレーニング
まっすぐ正面を向き顎を引き、首筋を伸ばす。10秒キープして3セット行います。
これらを毎日続けることで、顔全体の筋肉アップと二重顎の目立ちにくい状態を目指せます。専用グッズを使う際は医療や美容の専門家の指導や説明書に従いましょう。
悪習慣チェックと姿勢改善のストレッチメニュー
日常に隠れた悪い姿勢や癖は、知らず知らずのうちに二重顎の原因となります。特にスマートフォンやパソコン作業時の「スマホ首」や「猫背」、頬杖などの癖はフェイスラインが崩れるリスクが高まります。ご自身の習慣を下記のリストでチェックし、当てはまる場合は改善しましょう。
-
長時間スマホを下向きで操作している
-
パソコン作業で背中が丸くなっている
-
いつも頬杖をつく癖がある
-
ソファでだらしなく座ることが多い
こうした悪習慣を減らすためには、正しい姿勢を意識したストレッチが効果的です。
おすすめは「ネックストレッチ」と「肩甲骨ほぐし」。
- 首をゆっくり左右・前後に倒して10秒ずつ伸ばす。
- 肩を大きく回して肩甲骨を寄せる動作を10回繰り返す。
これらを1日数回行うことで、フェイスラインを美しく保つだけでなく全身の血行改善にもつながります。日常の小さな意識と習慣の変化が、健康的な小顔と自信に結びつきます。
最新の医療・美容クリニックで行う二重顎治療の種類と選び方
ハイフ(HIFU)、脂肪吸引、糸リフトの特徴と効果比較
二重顎の改善には多様な医療施術があります。近年人気のある方法は、ハイフ(HIFU)、脂肪吸引、糸リフトです。それぞれに特徴や効果、リスクがありますので、比較しやすいように下記の表でまとめます。
| 施術名 | 主な効果 | 特徴 | リスク・注意点 | 適している人 |
|---|---|---|---|---|
| ハイフ | 皮膚・脂肪層を超音波で引き締めリフトアップ | 施術時間短め、傷が残らない | 熱感、まれに一過性のしびれ | 軽度〜中度の二重顎、たるみ |
| 脂肪吸引 | 余分な脂肪除去で輪郭をシャープに | 劇的な変化が期待できる | ダウンタイム、腫れ・内出血 | 脂肪が多めの二重顎 |
| 糸リフト | フェイスラインのリフトアップ、小顔効果 | 直後から効果実感 | 糸の違和感や腫れ、術後に注意 | たるみ改善や小顔を目指す方 |
選び方のポイントは、自身の二重顎の原因(脂肪・たるみ・筋肉不足)や希望の変化に合った施術を選択することです。専門医のカウンセリングで現状をしっかり診断してもらうと安心です。
施術前後の注意点とアフターケアのポイント
施術前後の注意事項に気を配ることで、理想の効果と安全性を両立できます。主な注意事項は以下の通りです。
-
施術前のチェックポイント
- 健康状態や既往症の確認
- 服用薬やアレルギーの申告
- 適切な治療法の選択とリスク説明
-
術後のケアで気を付けること
- ハイフ後:強い摩擦や日焼けを避ける
- 脂肪吸引後:圧迫バンドの着用、腫れ・内出血への対処
- 糸リフト後:数日は強い表情や大きな口開けを控える
術後は腫れ、内出血、違和感などが生じることもありますが、正しいアフターケアと定期検診でトラブルを防げます。不安な症状が出た場合は、すぐにクリニックへ相談することが重要です。
信頼できるクリニック選びの基準と専門医の見分け方
安心して施術を受けるためには、クリニックや専門医の選び方が非常に重要です。以下に信頼できる医療機関のチェックポイントをまとめます。
-
クリニック選びの主な基準
- 施術実績が豊富で症例写真が多数掲載されている
- 詳細なカウンセリングを丁寧に行う
- 術後トラブルへのサポート体制がある
- 施術のメリット・デメリットを正しく説明してくれる
-
専門医の見分け方
- 医師が美容外科や形成外科の専門医資格を有している
- プロフィールや経歴が公開されている
- 学会所属や認定証の掲示がある
クリニックや医師に対する不安や疑問は積極的に質問し、納得したうえで施術を選ぶことが大切です。また、術後のフォロー体制や料金体系も事前に確認しておくと安心です。
顎を引くと苦しい・痛みがある場合の原因と対応
自律神経症状や筋肉・神経の緊張による影響
顎を引く動作によって苦しさや痛みを感じる場合、主な要因として筋肉や神経の緊張、自律神経の影響が考えられます。顎周辺の筋肉は日常の姿勢やストレートネックの影響で過度に緊張しやすく、血流が悪化することで違和感や痛みが現れやすくなります。デスクワークやスマートフォンの長時間使用により、首の筋肉がこわばり、顎の下に負担がかかりやすい状態が続くことも原因の一つです。
また、ストレスや疲労が重なった場合、自律神経のバランスが乱れやすくなり、首・肩・顎まわりの筋肉が無意識に力んでしまうことがあります。これにより首や顎への酸素供給が減り、圧迫感や痛み、不快感へとつながります。
| 原因 | 症状・特徴 | 例 |
|---|---|---|
| 筋肉の過緊張・こわばり | 痛み、重い感じ、つっぱり感 | 長時間のデスクワーク、猫背 |
| 自律神経のバランスの乱れ | 動悸、緊張、不安感、首肩のだるさ | ストレスや睡眠不足 |
| 神経の圧迫・炎症 | 痛み、しびれ、違和感 | 姿勢不良や過去の外傷・手術 |
適切なケアや姿勢改善に取り組むことで、多くの場合症状は軽減します。しかし、痛みが長引く場合は他の健康問題を考慮する必要があります。
痛みを伴う場合のセルフケアの注意点と専門家への相談目安
痛みや不快感がある場合、無理なマッサージや自己流の体操は避け、まずは下記のセルフチェックを行いましょう。
セルフチェックリスト
-
顎や首に力が入りきつく感じる
-
普段からスマートフォンやパソコンを長時間使う
-
痛みが数日以上続く、または悪化する
-
顎を引いた際につっぱりやしびれを感じる
上記に当てはまる方は、日常の姿勢を見直し、強い負荷をかけないことが大切です。痛みの予防には、正しいストレッチや軽い運動、十分な休息が効果的です。首や顎のトレーニングも一度にやりすぎず、専門家が推奨する方法を活用するとよいでしょう。
短期間で症状が改善しない、強い痛みやしびれ、違和感が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。特に首や顎に以前外傷歴がある方や、日常生活に支障が出ている場合には、神経や筋肉の検査が必要になることもあります。
| 相談の目安 | 備考 |
|---|---|
| 痛みや不快感が1週間以上継続する | 総合内科や整形外科が推奨 |
| しびれや感覚異常が広範囲に現れる | 神経内科受診を推奨 |
| 顎関節や首に明らかな変形・腫れがある場合 | 早期の専門診断が必要 |
適切な対応を行うことで症状の慢性化を防げます。痛みを我慢せず、気になる症状は専門家に相談しましょう。
二重顎に関するよくある質問とユーザーの疑問解消Q&A集
顎を引くやり方のコツは?
顎を引く際は、首の後ろを真っすぐに伸ばし背筋をしっかり立てた状態を意識しましょう。下記のポイントを押さえると自然な輪郭が引き出せます。
-
首を前に突き出さない
-
胸を広げて肩を落とす
-
顎の先端をやや後方・下に引く
失敗例としては、顎を強く引きすぎてシワや二重顎が目立ってしまう、または背中が丸まりストレートネックを招くことがよくあります。正しい姿勢を身につけるため、鏡で横顔のラインをチェックする習慣が大切です。
痩せているのに二重顎の原因は?
痩せていても二重顎になる場合、主な要因は脂肪以外の「骨格」や「筋肉の衰え」が挙げられます。顎が小さい、口周りの筋肉が弱い、加齢による皮膚のたるみ、リンパや血流の滞りも一因です。また猫背やスマホの使いすぎなど生活習慣の影響も大きいため、姿勢の見直しが重要です。実際に、ストレートネックや顎の骨格も二重顎リスクを高めると指摘されています。
ストレートネックと二重顎の関係は?
ストレートネック(首の湾曲が浅くなる状態)は、頭部が前に出てしまいフェイスラインを隠しがちです。この姿勢では顎下の筋肉や皮膚がたるみやすく、二重顎が強調されやすくなります。
-
デスクワークやスマホ操作が多い方に発生しやすい
-
長時間の悪姿勢が筋肉やフォームに悪影響
正しい首の湾曲を保つことで顔まわりのリフトアップにもつながります。首や肩をほぐすストレッチも効果的です。
すぐにできる二重顎解消法は何?
即効性のあるセルフケアとしては、顔や首周りのストレッチやマッサージが効果的です。特におすすめは以下の方法です。
-
舌を上顎につけて10秒キープ
-
首をゆっくり左右に伸ばすストレッチ
-
フェイスラインを指先でやさしくマッサージ
これらは自宅やオフィスでも手軽に実践できるため、毎日の習慣に取り入れてください。正しい姿勢を意識しながら行うことで、より高い効果が期待できます。
医療施術はどんな選択肢がある?
二重顎の医療的アプローチには、脂肪吸引・輪郭注射・HIFU(ハイフ)・糸リフト(スレッドリフト)など様々な施術法があります。
| 施術名 | 効果の特徴 | 適しているケース |
|---|---|---|
| 脂肪吸引 | 部分的な脂肪の除去 | 脂肪が多い場合 |
| 輪郭注射 | 脂肪の溶解・引き締め | 軽度〜中度の場合 |
| ハイフ(HIFU) | 超音波で皮膚を引き締め | たるみが気になる場合 |
| 糸リフト | たるみの引き上げ | 皮膚の緩みが強い場合 |
各施術には向き不向きやダウンタイムなども存在します。まずは専門クリニックで医師の診断を受けることが重要です。
顎を引いても二重顎にならない人の特徴は?
顎の骨格がしっかりしている、皮膚の弾力や筋肉量が十分にある、正しい姿勢や生活習慣を保っている人は、顎を引いても二重顎が目立ちません。過度な脂肪の蓄積やフェイスラインのたるみがないことも特徴の一つです。
顎が小さい・骨格による二重顎の解消法は?
筋肉トレーニングや姿勢矯正で一定の改善は期待できますが、骨格が大きく関与する場合は限界があります。医療施術や専門家のカウンセリングを活用し、自分に合った解消法を検討しましょう。
写真で二重顎が気になる時の対策は?
写真撮影時は、背筋を伸ばして少し顎を前に出し、正しい角度で写ることを意識しましょう。顔をやや下斜めに傾けると二重顎が目立ちにくく、小顔効果も期待できます。証明写真やスマホカメラの位置も工夫してみてください。
顎を引く癖があるけど苦しい場合は?
顎を引く姿勢で首や肩に違和感や痛みを感じる場合、無理なフォームになっている可能性があります。過度な力を入れず、自然な範囲で姿勢をキープしましょう。ストレートネックや他の症状が疑われる場合は専門機関の診断をおすすめします。
子どもや若い人でも二重顎になることは?
年齢に関わらず、骨格や姿勢、筋力不足、生活習慣が原因で子どもや若い方でも二重顎になることがあります。成長期や体型の変化に合わせた食事と運動、正しい姿勢を意識することが予防と改善につながります。